竹を使った花祭壇~故人様らしさを大切にした空間演出【事例集付き】
- 作成日: 更新日:
- 【 花祭壇 】
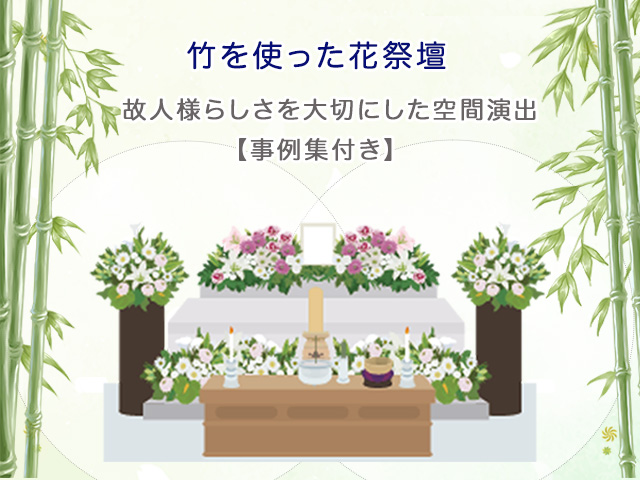
竹を使って花祭壇を作りたいというご要望は、叶えることができます。「竹は花ではないのに?」と思われるかもしれませんが、花祭壇は必ずしも花だけを使わなくてはならないという決まりはありません。竹を使うことで祭壇が「よりその人らしく」「より魅力的になる」と思えば、積極的に取り入れてもよいのです。
今回は「竹を使った花祭壇」をテーマに、竹を祭壇に取り入れる時のポイントや、実際に竹を使った花祭壇の事例をご紹介します。ぜひ最後までご一読ください。
1.花祭壇選びに役立つ「竹」知識

花祭壇に竹を効果的に取り入れるために、まずは竹の特徴と、竹がどのように日本で親しまれているかについて解説します。
竹の生態と特徴
竹はイネ科に属し、草と木、双方の特徴を持つ常緑性の多年生植物です。成長が非常に早く、草のように増殖する性質を持っていますが、木のように強度があります。そのため、竹は草とも木とも異なる独特な植物とされているのです。
竹は成長が早いことでも知られていて、中には1日で1メートル伸びたという記録もあります。しかし水分の蒸発度合や鮮度の低下も早いため、特殊な加工をしないと数日で変色が始まってしまいます。そのため、生の竹を祭壇に使うのは、弊社花葬儀を含めた一部の葬儀社に限られてしまうようです。
花葬儀がどのように生の竹を使うかは、この後の「花祭壇に竹を使うための工夫~花葬儀の場合~」にてご紹介します。
日本文化との結びつき
竹は建築、庭園、日用品、「道(どう)」と呼ばれる茶道や剣道の道具など、古来よりさまざまな用途に用いられてきました。また群生する竹は「日本らしい情景」として親しまれており、静岡の修善寺や京都の嵐山、東京の竹林公園など、各地に竹の名所が存在します。
日本古来の宗教である神道においても、竹は重要な存在であり、「笹の葉のついた竹は、神様が乗り移りやすい清浄な植物」であるとされ、地鎮祭や神事のお祭りに使われています。
さらに、竹から生まれたかぐや姫のお話「竹取物語」や、願い事を書いた札を笹に下げる「七夕」なども有名です。このように、竹は日本文化にとって非常に身近な植物なのです。
2.竹の魅力

竹の特徴や魅力について、もう少し具体的に見ていきましょう。
それぞれの特徴が花祭壇にどう生きるのか、ぜひ想像しながらご覧ください。
細長くまっすぐな形状
竹はどんなに大きく成長しても一定以上は太くなりません。細長く、まっすぐな形状のまま、20メートルほどの高さまで成長します。スリムなラインが放つ美しさは、見る人にスタイリッシュで洗練された印象を与えてくれます。
節の存在
竹には一定の間隔で「節」があります。この節によって、シンプルな竹に視覚的なリズムとパターンが生まれ、見る人の目を楽しませてくれるのです。
竹の節の面白い特徴として、節すべてに「生長点」が存在することが挙げられます。成長点とは、植物が成長するために細胞分裂を行うところで、仮に一本の竹に50個の節がついており、それぞれの成長点が1日に1センチメートル伸びた場合、稈は1日で50センチメートルも成長することになります。
竹の節は成長の早さだけでなく、「力強い生命力」や「向上心」の象徴とも捉えられています。
緑色の美しさ
日本の伝統色には、成長と共に変化する竹の色を表す「若竹色」「青竹色」「老竹色」があります。青々とした緑色や、グレーがかった緑色といった色までさまざまで、涼し気で上品な印象があります。
竹の色合いは、和花・洋花問わず四季の花々と調和しやすいため、組み合わせる花の種類によってさまざまな雰囲気を作り出します。
堅さとしなやかさを併せ持った細長い葉と枝
竹は、堅さとしなやかさ両方を兼ね備えた珍しい植物です。中が空洞で、表皮に近いほど繊維の密度が高いため、折れにくい柔軟性を持っています。
堅くしなやかな竹ですが、「縦方向に割れやすい」という特徴もあります。これは、竹の繊維が縦の向きに並んでいるからであり、この特徴から「竹のように真っ直ぐで潔い性格」を意味する「竹を割ったような」という言葉が生まれました。
風に大きく揺れる動きや、それにより細長い葉がこすれる音は、その場にいるだけで癒しを与えてくれるでしょう。
3.竹の花祭壇で表現できること
前述した竹の特徴や魅力を生かして、花祭壇ではどのような表現ができるのでしょうか。
一般的な例をご紹介します。
力強い様、雄々しさ
柔らかい印象となりがちな花祭壇に、真っすぐに伸びる竹のラインを設置することによって、力強さや雄々しさ、揺るぎのない思いを演出することができます。祭壇の両端に竹を設置すると、「精悍(せいかん)さ」や「一本芯の通った印象」を表すことができ、より強い印象を与えることができるでしょう。
「和」や日本の風情
竹は古くから日本全国に分布している、日本を象徴する植物のひとつです。竹を花祭壇に飾ることによって、「和」や日本らしい風情を演出することができます。伝統的な和の雰囲気を大事にしたい方や、日本らしい風景を再現したい方などにおすすめです。
自然や季節感
竹は常緑性の植物であり、竹そのものに特定の旬の時期は存在しません。しかし、竹から生えるタケノコの収穫期や、短歌に登場する機会の多さから、春~夏にかけての季節と結びついて考える傾向があります。七夕の時期に、短冊を付けた竹をよく見かけることも、その理由のひとつでしょう。
秋・冬を表現する場合には、紅葉した紅葉や、冬の雪を表すかのような白い花とあわせて使い季節感を演出することも可能です。
季節の花々と合わせて、旅立ちがより華やかになるような表現をしてみるのはいかがでしょうか。
清浄さ、神々しさ
前述したように、竹は神事において「清浄な植物」です。葬儀は故人様の死を悼む厳かな儀式ですから、竹を用いて儀式にふさわしい空気感を作ることもできます。
静けさ、安らぎ
大切な人を見送る時間は、とてもつらいものですが、花祭壇に竹を取り入れることによって、さまざまな効果が期待できます。鮮やかな緑色や精悍なたたずまい、柔らかな揺らぎが、花祭壇に静けさをもたらしてくれます。清涼感や優しさもあいまって、深い悲しみの中にいるご遺族に安らぎを与えてくれるでしょう。
4.花祭壇に竹を使うための工夫~花葬儀の場合~
竹は常緑性であり、通年で生えているものですが、実は鮮度を保つことがとても難しい植物です。切り取って1日も経つと全体が茶色く変色し、笹の葉は乾燥して枯れてしまいます。
そのため多くの葬儀社では、生竹ではなくプラスチック製の竹を使うのが一般的です。イミテーションの植物は枯れることがなく、扱いが簡単で、価格も抑えやすいメリットがあります。
しかし花葬儀では、植物本来が醸し出す生命力や躍動感、儚さを見る人に感じてほしいという思いから、プラスチック製ではなく、市場で仕入れた生の竹に彩色を施して使用しています。これは、生花にこだわった花祭壇をお作りしている花葬儀ならではの試みです。
人が手を加える工程はどうしても必要ですが、見た目の劣化を気にすることなく本物の竹を通年で使うことができます。実際に見比べた時に、プラスチックの竹と本物の竹では、質感が全く違うことを実感いただけるでしょう。
なお、花葬儀では、市場で仕入れた切り立ての竹や竹の苗を、そのまま祭壇に使うこともあります。詳しくは後述する「苗や生竹を使うことも」をご覧ください。
5.花祭壇における竹の役割、使い方~花葬儀の場合~

竹は、工夫次第でさまざまな花祭壇の演出に取り入れることができます。
こちらより、花葬儀における竹の使い方について、詳しくご紹介します。
演出資材として使うことが多い
花葬儀では、竹を「祭壇の演出資材」として使うことが多くあります。演出資材とは、メインとなる花祭壇の雰囲気やテーマに合わせ、見る人により深い感動や癒しを与えるために設置する「名脇役」のことです。
詳しい演出方法は、以下をご覧ください。
斎場全体の空間を演出
一般的な花祭壇は、白木祭壇から大きくはみださないように花が生けられるため、全体のフォルムに大きな違いは見られません。
しかし花葬儀では、祭壇のみならず、葬儀斎場全体を通じてテーマを表現することに重きを置いています。祭壇の周辺に限定せず、自由な発想で竹を配置し、一体感のある空間を作り上げます。
本来の直立した形だけでなく、斜めに配置したり、加工して曲げた竹を斎場内に飾ったりすることも可能です。花とあわせて動きのあるシルエットにすることで、オリジナル性の高い空間を演出することが可能です。
生花の脇役としての演出
竹の緑色は、生花との相性が抜群です。色鮮やかな花々に緑を加えることで、花の美しさがより一層引き立ちます。生花のメインカラーを際立たせたいや、生花を生けるための花器としてなど、さまざまな用途で能力を発揮します。
小物としての演出
前述したとおり、竹は古来より日用品や建築物などに使用され、伝承にも登場した身近な植物です。「故人様は竹トンボづくりが上手だった」「かぐや姫のお話が大好きだった」など、故人様にゆかりのある竹の小物を祭壇や斎場内に飾ることで、大切な人との思い出をより鮮明に思い起こすことができるでしょう。
テーマを表現するための演出
以下のような祭壇のテーマを表現するために竹を使うこともあります。
・和テイストの葬儀にしたい
・故人様が大好きだった思い出の竹林を再現したい
・日本の伝統的な植物を使って、スタイリッシュな祭壇を作りたい
・緑がいっぱいの、安らぎを感じさせる雰囲気にしたい
季節を表すための演出
祭壇で季節感を表現する理由は、人さまざまです。「故人様の誕生した季節で温かく見送りたい」「七夕の時期に亡くなった故人様の思い出を大切にしたい」「初夏のようにさわやかな人柄を表現したい」などに基づいて選ばれることがあります。季節感を重視する祭壇において、季節を表すための演出として竹を使うこともあります。
苗や生竹を使うことも
「人の手がなるべくかかっていない、切り立ての竹を使いたい」というご要望をお持ちのお客様に対しては、切ったばかりの竹や、竹の苗を市場から仕入れて使うこともあります。
ただし、条件に合う生竹が常に市場に並んでいるとは限らず、また笹の葉はすぐに乾燥して変色するため、仕入れた時と同じ見た目を維持できるかはケースによって異なります。さらに、「仕入れた竹を切ったり、生けたりする時間を葬儀前に確保できるか」を考えることも必要です。
しかし、花葬儀ではお客様の「こうしたい」という想いに応えるために、全力を尽くしますので、まずはご要望を遠慮なくお話ください。
6.【花葬儀】竹と花が織りなす祭壇演出

多くの花祭壇は、カタログの中にある見本の中から好みに合うものを選びますが、花葬儀では、「その人らしさが感じられ、いつまでも心に残る葬儀を行ってほしい」という思いから、ひとつひとつの花祭壇をオーダーメイドでお作りしています。
お客様の希望が反映され、故人様らしさが伝わる祭壇を作るには、事前の綿密なヒアリングが重要です。お客様が自覚されていない部分の要望まで引き出し、イメージを共有して調整を重ねることで、世界でただひとつ、その方のためだけの花祭壇が完成するのです。
ここからは、オーダーメイドにこだわる花葬儀による、竹を使った特別な花祭壇の演出アイディアをご紹介します。
「真っすぐ」「生き生き」といった故人様のお人柄を体現
真っすぐに伸び、成長の早い竹は、故人様のお人柄を表現するのにぴったりです。過去には、「竹のようにさっぱりしたご性格」である故人様のために竹を使用したこともありました。
竹はそのままの形で使うだけでなく、縦に細く割いて曲げたり、筒状にカットしたりすることで、さまざまな表現が可能です。
「曲がったことの嫌いな、まっすぐなご性格」「個性的なものに心を惹かれる方だった」「勉強熱心で、どんなことでも習得するのが早かった」「しなやかで、凛とした振る舞いが美しかった」など、大切な方の一番好きなところを竹で表現することで、故人様をより身近に感じる花祭壇となるでしょう。
故人様の趣味、ご職業などを表現
生涯を通じて熱心に取り組まれていた故人様のご活動を、花祭壇でたたえたいという方は多くいらっしゃいます。そのような場合は、竹を使って、手掛けてきたお仕事の一部を再現したり、竹が使われている趣味の道具(弓道や茶道、工芸品など)を斎場内に飾ったりするのはいかがでしょうか。
故人様のお仕事や趣味について、雰囲気から感じ取ってもらうような使い方もよいでしょう。例えば「会社の近くに立派な竹林があった」「毎年夏になると流しそうめんの装置を竹で手作りしてくれた」などの思い出を間接的に表現することで、参列者同士が故人様の思い出を共有するきっかけとなるかもしれません。
長い竹を天井いっぱいに使ったダイナミックな設計
花葬儀が普段祭壇に使用する竹の長さは約3mです。葬儀社の中でも、これほどの長さの竹を頻繁に使っているところはまれです。
長い竹を使用することで、斎場の大きさいっぱいに広がるダイナミックな祭壇を設計することができます。設置する花や竹の長さを変えることで会場に奥行が出て、より個性的な空間の演出が可能です。
白砂利や和傘などの小物と合わせた演出
「和」を演出したい方にも、竹はおすすめです。竹と花に加え、白砂利や和傘、時には苔などの小物と合わせ、細部にまでこだわった演出を行います。
こうした細部へのこだわりは、見る人の心に必ず残ります。「素敵な祭壇だった」「今までにない良い葬儀だった」という思い出が、ご家族のこれからの支えとなるよう、花葬儀はご家族と共に祭壇を作り上げます。
竹を切って花器として使用
花葬儀で使う花器(花を生ける器)は、ガラス製やアイアン製など、葬儀の雰囲気に合わせてお選びいただけます。ご希望に応じて、切った生竹を花器として使用することも可能です。
例えば、竹の花器にボタンの花や紅葉を挿し、祭壇の周りや斎場の床に置くことで、自然な風合いを大切にしつつも独自性のある空間を創出することができます。さまざまなアレンジや工夫ができる点は、花葬儀ならではのメリットのひとつと言えるでしょう。
思い出の場所、風景の再現
竹と花を使って、思い出の場所や風景を再現する方法もあります。たとえば、「故人様の好きなものでたくさん囲んであげたい」「楽しかった思い出を振り返りたい」といった想いを表すこともできます。
また、故人様の闘病生活が長く、「好きな場所に行きたくても行けなかった」という場合、その場所を祭壇で表現することで、願いを叶えてあげることもできるでしょう。ご自宅の庭、家族旅行で訪れた場所、映画や小説であこがれた風景……そういったものの中に竹があれば、ぜひ使ってみてはいかがでしょうか。
季節の花と合わせてスタイリッシュな空間を演出
季節の花と竹を組み合わせた花祭壇は、以下のように幅広い印象を与え、全体的にスタイリッシュな空間を作り上げることができるでしょう。
| 季節 | 使用する花の例 | 印象 |
| 春 | 菜の花+竹 | 柔らかな黄色と爽やかな緑色で、心地よい印象に |
| 夏 | アジサイ+竹 | 深みのある落ち着いた色味によって、しとやかで静けさのある雰囲気を醸成 |
| 秋 | コスモス+ススキ+竹 | 淡いコスモス、しなやかに揺れるススキ、まっすぐ伸びる太い竹で、原野のようなのどかな風景を再現 |
| 冬 | ツバキ+竹 | はっきりとした強い赤と緑のコントラストで、インパクトのある印象に |
光や水音まで考えた雰囲気作り
上記に挙げた例に加えて、花葬儀では光や音を使った演出も得意としています。光と音の演出例は以下の通りです。
・竹を下からライトアップする
・切った竹の中に電飾を入れて、キャンドルとして祭壇の周りに飾る
・水や鳥のBGMを流す
他にも、扇風機を植物にあてて自然な風のゆらぎを生み出したり、故人様のお好きだった香りを斎場で焚いたりすることもできます。故人様らしさを五感で感じられる空間にすることで、幻想的な雰囲気が生まれるでしょう。
白木祭壇を使わずに「いけばな」だけで全体を装飾
一般的な仏式のお葬式では、白木で作った「白木祭壇」を使用します。白木祭壇は日本の古くからの葬儀に使われる伝統的な祭壇ですが、宗教感のない葬儀や個性的な葬儀を望む場合は、白木祭壇を使わない方法もあります。
花葬儀は生花祭壇を得意としておりますが、「生け花」だけで葬儀会場を装飾するという方法も可能です。花葬儀ではこれを「いけばな祭壇」と呼び、華道家の勅使河原城一氏の監修のもとご提供しています。
生竹を使っていけばな祭壇をつくる場合、設営時間が十分に確保できるかどうかが重要です。通常、葬儀の設営時間は1時間半ほどですが、竹を切って生け花にするためにはそれ以上の時間を要します。準備に十分な時間を取れる場合などは可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
7.【花葬儀】竹を使った花祭壇実例
最後に、これまで花葬儀で手掛けてきた花祭壇の中から、竹を使った実例をご紹介します。
竹の花祭壇に興味をお持ちの方は、ぜひ参考になさってください。
祭壇名:和モダンテイスト×JAZZ

祭壇名:和モダンテイスト×JAZZ
黄、紫、赤の花に竹を合わせた、和モダンな印象を与える祭壇です。ジャズがお好きだった故人様のために斎場のBGMとしてジャズを流し、故人様らしい、それでいて調和のとれた空間を作り上げました。
祭壇名:山寺のような

「山寺の庭」がテーマの祭壇です。白、緑をベースにした、モダンでスタイリッシュなスタイルをご希望されました。山寺でよく見かける竹を並べ、苔や鉢植えのアジサイで庭の雰囲気を創出しています。
祭壇名:竹と桜の祭壇

故人様への感謝の気持ちを表した祭壇です。竹を割ったような、真っすぐで優しさあふれる故人様のご性格を、竹と柔らかい色調の花で表現しました。竹をクロスさせることで、視覚的なリズムを生み出しています。
祭壇名:春和景明(しゅんわけいめい)
春和景明とは、春の日の穏やかで、明るい陽気のことです。故人様の元気で明るいイメージが表現できるよう、ピンクを基調とした花で祭壇を飾っています。メモリアルコーナーでは、家族旅行で訪れた京都を竹や和傘などを使って表し、故人様がより身近に感じられる空間となりました。


祭壇名:冬のいけばな祭壇

こちらは「いけばな祭壇」の事例です。白木祭壇を使わずに、竹とお花だけで棺を囲っています。存在感のある竹を上手に使うことで、他にはない荘厳さや高貴さを表します。
祭壇名:自宅の窓から

長い闘病生活で、ご自宅に帰ることが叶わなかった故人様のために、ご自宅の窓からの風景を再現したのがこちらの祭壇です。より「本物らしさ」を追求するために、竹や背の高い木を天井いっぱいまで使いました。寄せられた供花を、祭壇を挟むように並べ、故人様が多くの人から愛されていたことを象徴的に表しました。
花葬儀ではご依頼ごとに仕入れを行うため、取り扱う植物の種類が豊富です。竹以外にもさまざまな花や木を使った演出を行うことができます。竹以外の祭壇実例は「花祭壇ギャラリー」に掲載しておりますので、こちらもあわせてご覧ください。
8.竹を使った花祭壇で心からのお見送りを
日本人にとってなじみ深い竹は、強い生命力としなやかさを持った魅力的な植物であり、祭壇においてさまざまな表現を可能とます。大切な方のための葬儀に、ぜひ竹を使った花祭壇を設けて、温かく心に残るお見送りをしてみてはいかがでしょうか。
お客様との対話を大切にする花葬儀では、無料の事前相談を承っております。葬儀プランや花祭壇のデザイン、葬儀で叶えたいこと、不安なこと、どのようなことでもご遠慮なくお話ください。事前相談のお申込みは、インターネットの他、24時間365日対応しているお電話でも可能です。どうぞお気軽にご連絡ください。




























