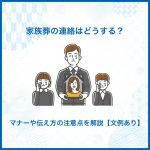お通夜の過ごし方~当日にご親族がすべきこと、前日までに行う準備も解説
- 作成日: 更新日:
- 【 葬儀・葬式の基礎知識 】

告別式(葬儀)の前日に行われる「お通夜」。参列する機会はあっても、執り行った経験がなければ、必要な準備や、参列者のお迎えの仕方がわからず、困ることもあるでしょう。
今回はお通夜の過ごし方について、通夜振る舞いや通夜後の寝ずの番まで含めて詳しくご紹介します。お通夜の準備を始めようとしている方、お通夜への参列を控えている方も、ぜひ、参考にしてください。
【もくじ】
1.なぜお通夜を開くのか

最初に、お通夜を行う意味、告別式との違いを解説いたします。
お通夜の意味
お通夜はもともと、「夜を徹して神仏に祈りを捧げること」が目的で、一晩中灯りを絶やさず、故人様を見守る儀式でした。また、かつては生死の見極めの技術が未発達だったため、亡くなったと診断された後に蘇生することもありました。そのため、亡くなったことを正確に確認する時間を作る必要があるという理由もあったとされています。
かつてのお通夜は、故人様を偲び、ロウソクや線香を絶やさぬよう一晩中見守るという形式が一般的でした。しかし、現在は「半通夜」と呼ばれる、日付が変わらないうちに弔問客が退席するという形式が多くなっています。
告別式との違い
2日にわたって行われるお通夜と告別式ですが、どのような違いがあるのかを見てみましょう。
・お通夜:ご家族、ご親族など、故人様との関係の深い人が冥福を祈る儀式
・告別式:友人、知人、ご近所の方、仕事の関係者など、故人様と縁のあった人が別れを告げる儀式
つまり、故人様に別れを告げる人が誰であるかによって、参加する式が分けられていたといえます。
しかし近年は、昼間に執り行われる告別式に出られない人が、お通夜に参列することも増えてきました。このため現在のお通夜は、「昼間の都合がつかない人の別れの場」ともいえるでしょう。
2.お通夜当日の喪主様、ご親族の過ごし方

こちらでは、お通夜当日の喪主様やご親族の過ごし方を解説していきます。
会場集合、受付
会場入りは、開式1~2時間前が目安です。事前の打ち合わせで決めておいた「お香典の受け取り」「受付への案内」など、各々の役割分担や段取りを葬儀社の担当と一緒に確認します。
なお、受付は現金を取り扱うため、葬儀社には依頼せず、ご遺族側で対応することがほとんどです。参列者の人数にもよりますが、順番待ちの列が長くなることを避けるため、受付係は基本的に2名以上必要です。
お通夜開始
僧侶が到着されると、お通夜がはじまります。具体的な内容は以下のとおりです。
読経・焼香
読経の時間は、通常30分から40分ほどです。参列者は静かに耳を傾け、故人様をしのびます。読経と同時進行で、焼香を随時進めます。基本的に「喪主様→ご遺族→ご親族→一般参列者」の順番でおこない、参列者の人数によって所要時間は変わります。
僧侶の法話
近年は省略されるケースも増えてきていますが、読経の後5~10分ほど、法話をされることもあります。法話が終わると、僧侶は退場します。
喪主挨拶
喪主様がご遺族を代表して挨拶します。お通夜の喪主様の挨拶に盛り込む内容はおもに「参列、生前の厚意に対する感謝」「告別式の日時の案内」「通夜振る舞いの案内」などです。
「故人様との想い出」などは、余裕があれば話す程度でかまいません。流ちょうに、うまく話せなくても大丈夫です。それよりも、故人様や参列者に対する感謝の気持ちを伝えることを大切にしましょう。
通夜振る舞い
別室に通夜振る舞いの席を準備し、参列者をそちらにご案内します。最初と最後に、喪主様から通夜振る舞いの挨拶をしましょう。
最初の挨拶の内容は下記のとおりです。
・弔問に来ていただいたことへのお礼
・遠慮なく飲食してほしいこと
通夜振る舞い最後の挨拶では、翌日の告別式の開催場所と時間を伝えることが一般的です。
基本的に通夜振る舞いの席は1~2時間程度ですが、参列者の多くが30分程度と早い段階で退席するなど、1時間後にはほとんど人が残っていないこともあります。そのため、終了時の挨拶は柔軟に、タイミングを見てするほうがよいでしょう。
なお、僧侶にも通夜振る舞いへの参加の声かけはしましょう。ただ、スケジュールの都合で断られることもあるので、その場合は御膳料で代えるようにします。白い封筒に「御膳料」と縦書きし、お車代(僧侶の交通費として渡すお金)とともにお渡ししましょう。
棺守り(寝ずの番)
通夜振る舞いの後、僧侶や一般参列者が帰宅すると、故人様に寄り添う時間となります。これを「棺守り」と呼び、寝ずの番、夜伽(よとぎ)、線香番などとも呼ばれています。ロウソクと線香の火を絶やさずに見守ることで、ご遺体に魔がつくことを防ぐとされてきました。
しかし近年では、寝ずの番を行うことは、減少する傾向にあります。また、防災・防犯上の理由から、以下のような制限がある斎場が増えています。
・深夜にロウソクや線香に火をつけることが禁止されている斎場
・宿泊不可、深夜の出入りを禁止している斎場
翌日には告別式も控えているので、とくに心身ともに消耗されている場合、無理をせず休息を取ることが大切です。
寝ずの番に関して詳しく知りたい方は、「寝ずの番の意味や過ごし方」に関する記事で解説しておりますので、ぜひ、そちらをご覧ください。
3.お通夜までの準備・過ごし方

お通夜当日の喪主様、ご親族の過ごし方をご説明いたしました。ここからは、喪主様、ご親族が、お通夜までにどのような準備しながら過ごすのかを解説いたします。
場所や喪主の決定
・会場や具体的なお通夜(葬儀)の内容
・喪主を誰にするか
など、葬儀社の担当と相談して決めます。
喪主は、ご遺族内で相談して誰にするかを決めます。一般的には故人様とのご関係で、以下の順に最初に当てはまる方が務めます。
1.遺言などで指定された方
2.配偶者様
3.成年になられた男性のお子様
4.成年になられた女性のお子様
5.ご両親
6.ご兄弟
7.それ以外で故人様とご関係のあった方
【例】親しいご友人、(施設で亡くなられた場合は)施設長様など
また、菩提(ぼだい)寺がある場合は、僧侶のスケジュールも必ず確認しましょう。その連絡は、喪主様をはじめご家族の方がする必要があります(葬儀社が対応するとトラブルに発展することもありますので、葬儀社としてもご家族の方からの連絡をお願いしています)。
関係者への連絡
故人様のご親族や親しい方を中心に、訃報を順次連絡します。以下の点は必ず伝えるようにしましょう。なお、連絡方法は、電話やメールが一般的です。
・故人様の名前
・亡くなった日時
・お通夜、葬儀の開催日時と場所
・喪主様のお名前
・連絡の担当者または葬儀の責任者の連絡先
連絡をする順番は、基本的に「ご親族→故人様の関係者(友人、知人、職場や学校関係)→ご遺族の関係者(友人、知人、職場や学校関係)→町内会、隣近所」です。
なお、場合によっては、訃報をお伝えする相手に連絡がつかないことも考えられます。その場合はお電話口の方に「訃報をお伝えしたい相手のお名前」と「連絡しているご自身のお名前」をあわせて伝え、訃報の旨の伝達をお願いするようにしましょう。
通夜振る舞いの用意
お通夜の閉会後に開く、故人様の供養と参列者への感謝の意を表す食事の席を、通夜振る舞いと呼びます。そのための料理と飲料を用意するのですが、基本的には希望を伝えたうえで葬儀社に依頼すれば問題ありません。
これまではオードブルのような大人数で取り分けられるようなものが一般的でしたが、近年は、人数分の弁当を用意することが増えています。
また、伝統的に、お酒には「穢れ(けがれ)を清める」という意味が込められているため、通夜の席ではアルコール類を用意することが一般的です。ただし、自動車で来場される方や、お酒を飲めない方のために、ノンアルコール飲料も準備しておきましょう。
返礼品、会葬礼状の手配
会葬礼状とは、お通夜、葬儀に参列いただいた方へのお礼状です。本来は葬儀後に郵送するものなのですが、近年は返礼品とともに手渡すことが多くなってきています。返礼品や会葬礼状は、いずれも葬儀社に依頼するとスムーズでしょう。
4.お通夜の日取りを決める際の注意点

お通夜は、告別式の前日に執り行います。ご逝去から早い段階で日取りを決められればよいのですが、以下の理由で時間がかかるケースもあるので注意しましょう。
葬儀場、火葬場が混雑している
とくに都市部は混雑が激しくなってきており、複数の葬儀場、火葬場の空き状況を確認する必要があります。葬儀社が確認してくれるので、そちらにおまかせしてもよいでしょう。
友引が重なる
友引の日の葬儀が禁止されているわけではありませんが、「親しい人が冥界へ引き寄せられる」ことを連想させるため、避けることが多いようです。また、友引の日はお休みの火葬場も多いので、お通夜や葬儀を行う日の選択の幅は狭くなってしまいます。
遠方からの参列者が多い
故人様の現住所と故郷が離れている場合、ご参列者は宿泊場所の確保が必要になります。近い日程で宿を確保できないことを考慮し、お通夜や葬儀まで多少日程を空けることがあります。
僧侶のスケジュールが確保できない
仏教の場合、お通夜、告別式ともに読経をすることから、僧侶を呼ぶ必要があります。その都合がつかなければ、日程の変更を考えなければなりません。ご家庭とお付き合いのあるお寺(菩提寺)がある場合は、そちらに依頼しましょう。
5.お通夜を行わない形式の葬儀
一日葬(告別式と火葬だけおこない、一日で葬儀を完結させるもの)や火葬式(火葬のみおこなう、一日葬をさらに簡略化させたもの)であれば、お通夜なしで葬儀ができます。この形式の葬儀のメリットとデメリットを見ていきましょう。
◎一日葬・火葬式のメリット
・葬儀費用を抑えられる
・ご遺族側の精神的、肉体的な負担が減る
◎一日葬・火葬式のデメリット
・安置場所や使用する施設によっては、その使用料が2日分必要になることがある
・昼間の都合がつけられない(お通夜にしか参列できない)方に対応できない
・お付き合いのあるお寺(菩提寺)のご意向次第では、お通夜の省略を認めてもらえないことがある
とくに菩提寺のご意向の確認は必須です。お通夜を営まないことでトラブルに発展することも考えられますし、最近は葬儀よりもお通夜の参列者が多いこともあります。一人での判断は避け、ご親族やお寺への相談、確認を忘れないようにしましょう。
6.お通夜の過ごし方に関するQ&A
A.お通夜の前日は、故人様を見送る心の準備を整えるとともに、通夜や葬儀の服装や持ち物、出棺時に入れる物の最終確認をするなどして過ごします。
関係者への連絡、通夜振る舞いや返礼品、挨拶状の準備などは事前に行えるため、前日でなければできない準備は基本的にありません。お通夜までの日程が短く、やむを得ず準備が前日に集中した場合は、葬儀社に相談しながら優先順位をつけて進めることが大切です。
A.お通夜の際のご親族の服装は、一般的な喪服である準喪服を着用します。
準喪服は男性なら黒のスーツ、女性なら黒のワンピースかアンサンブルなどです。なお、急な訃報を受けてお通夜に参列する場合、喪服でなくとも、控えめな色合いの普段着で差し支えありません。
寝ずの番を行うときの服装は、自宅で家族のみの場合はジャージやパジャマでもかまいませんが、ご自宅以外やご親族が集まる場では、控えめでシンプルなデザインの服を心がけましょう。
A.お通夜に参列する際に持って行く物は以下のとおりです。
・お香典と袱紗(ふくさ)
お香典は、袱紗に包んで持参します。袱紗はハンカチで代用することができます。
・ハンカチ
白または黒の無地が適しています。派手な柄や色物は避けます。
・数珠
仏式の葬儀では、数珠を持参します。ただし、必須ではなく、ご自身の宗派の数珠でも問題ありません。
なお、故人様、あるいは喪主様と住まいを同じくするご家族は、お香典を持参しないことが一般的です。故人様や喪主様と生計を共にしていないご親族は、お香典を用意するのがマナーです。
7.お通夜は故人様を想いながら心穏やかに過ごしましょう
大切な方がお亡くなりになったという悲しみの中で、お通夜の準備を進めることは、とても大変なことだと思います。しかし、故人様とともに過ごせる最後の夜です。故人様への想いをあらためて深め、故人様の旅立ちを皆で静かに見送るお通夜のひとときを、どうぞ大切にしてください。
お通夜の過ごし方、準備の仕方について、わからないこと、気になることがあれば、花葬儀の事前相談までお気軽にお問い合わせください。故人様の旅立ちを悔いなく見送れるよう経験豊富なスタッフが、お客様の疑問に的確にお答えし、精一杯お手伝いさせていただきます。