家族葬の連絡はどうする?マナーや伝え方の注意点を解説【文例あり】
- 作成日: 更新日:
- 【 葬儀・葬式の基礎知識 】
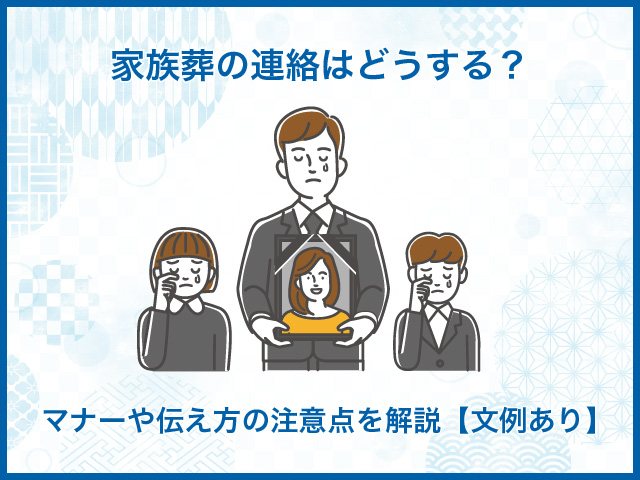
近年、故人様を近しい方々と見送る「家族葬」を選択するご家族が増えています。限られた方のみに参列いただくため、「参列いただかない方への伝え方は?」「気をつけるべき注意点は?」など、悩む方もいることでしょう。
そこで今回は、家族葬の連絡で「誰に」「いつ」「どのように」伝えるべきか、具体的な文例と共にご紹介します。家族葬を検討している方、家族葬を予定されている方は、ぜひ、この記事を参考になさってください。
【もくじ】
1.家族葬でも訃報・葬儀の連絡は必要

家族葬であっても、訃報・葬儀の連絡は必要です。家族葬の定義とともに、その理由を解説します。
そもそも、家族葬とは
家族葬に明確な定義はありませんが、一般的には参列者を限定し、身内や親しい人のみで執り行う葬儀を指します。故人様との親しい方々との時間を大切にし、落ち着いた雰囲気の中でお別れができるのが特徴です。
家族葬は必ずしも小規模になるとは限りませんが、参列者を絞り込むからこそ、誰にどのように連絡するかが重要になってきます。連絡範囲や方法を誤ると、故人様やご遺族の意向が伝わらず、トラブルにつながる可能性もあるのです。
参列いただかない方への連絡は葬儀後に行うことも
故人様と親しい間柄の方には、できるだけ葬儀前に訃報・葬儀の連絡をすることをおすすめします。「事前に知らせてほしかった」といった心残りの声も少なくないためです。
ただし、全ての方に葬儀前の連絡が必要というわけではありません。特に、故人様との関係性が薄い方や、ご遺族の意向で参列を見送らせていただいた方には、葬儀後に報告する選択肢もあります。
そのような場合でも、何らかの連絡をすることが大切です。連絡をしないままにすると、ご家族以外の人から訃報や葬儀を知らされた際に、不快に思われる方がいらっしゃるかもしれません。葬儀後であっても、適切なタイミングで報告することを心がけましょう。
2.家族葬の連絡はどこまでの人にする?範囲の考え方
家族葬の連絡をどこまでの人にするかは、ご遺族の判断にゆだねられます。参列者を限定する葬儀なので、すべての方に一律の連絡をする必要はありません。「この人には亡くなったことだけを伝える」「この人には葬儀の詳細も知らせる」など、整理して連絡するとよいでしょう。
家族葬の連絡の範囲を決める際には、次のような基準が参考になります。
- ・エンディングノートなどに参列してほしい方のリストがあれば尊重する
- ・故人様が生前、最後に会いたいと思う相手だったか
- ・ご遺族が今後も関係を継続させたい方かどうか
誰に葬儀の連絡をするかは、ご家族でよく話し合い、故人様の想いとご遺族のお気持ちを大切にしながら決めていきましょう。
3.家族葬の連絡手段は何が良い?
家族葬の連絡は、相手との関係や状況に応じて適切な手段を選ぶことが重要です。主な4つの手段について特徴や注意点を解説します。
電話
最も迅速かつ確実に葬儀について伝えられる手段が電話です。特にご家族やご親族など、故人様と近しい方で葬儀に参列いただきたい方には、できるだけ早く知らせることが重要であるため、電話が適しています。
電話でのご連絡後、家族葬の詳細については、メールやはがき、手紙などの書面で補足すると安心です。文書での情報共有により、行き違いや誤解を防ぎ、相手にも確実に内容をお伝えできます。
メール
仕事関係の方やいつもメールでやり取りをしている方への連絡には、メールの利用も検討できます。印刷や郵送の手間がなく、短時間で複数の方へ送信できるため、スムーズな連絡が可能です。特に、仕事上の関係者には、電話よりメールのほうが相手の都合がよい場合があるでしょう。
ただし、対面や電話と比べて誠意が伝わりにくい面があります。そのため、メールでの連絡が適切か、相手との関係性を考慮するなどの注意が必要です。
LINE等のSNSアプリ
家族葬について親しい友人やご家族へ連絡する場合は、LINEなどのSNSアプリも選択肢のひとつです。特に若い世代は、日常的にLINEやFacebookなどのダイレクトメッセージでやり取りをしており、違和感なくスピーディーに伝えられます。
ただし、SNSは相手や場面によっては適切でないため、メールと同様に使用する相手や場面には注意が必要です。家族葬の内容は個人的な情報ですから、X(旧Twitter)やInstagramなどの公開アカウントで発信するのはマナーとして避けましょう。
手紙・はがき
手紙やはがきでの連絡は、受け取られる方に丁寧な印象を与えます。ただし、郵送には時間がかかるため、電話やメールで先に伝え、その後に家族葬の詳細を手紙やはがきで送ってもよいでしょう。
家族葬では葬儀後に訃報や葬儀の報告をすることもありますが、手紙やはがきであれば、失礼なく相手への敬意や感謝の気持ちを伝えられます。
なお、故人様の友人・知人や生前お世話になった方に、ご遺族が故人様の訃報や葬儀について、はがきやカードで知らせる方法は「死亡通知」と呼びます。
4.家族葬の連絡をすべき相手とタイミング

家族葬の連絡は、参列いただくかどうかや、故人様・ご遺族との関係性などによって異なります。こちらでは、一般的に早い段階で連絡すべき順に、タイミングや連絡方法を解説します。
ご家族や親しいご親族
近しいご家族やご親族へは、できるだけ速やかに家族葬の連絡を行います。電話で伝えることが一般的で、お互いの声を通じて感情を共有し、気持ちに寄り添うことができます。家族葬を選択した理由や、家族葬の規模や内容、今後の段取りなどについても伝えておくと、ご家族やご親族の不安を和らげることができるでしょう。
故人様の勤め先
故人様が現役の会社員だった場合は、勤め先には早急に家族葬の連絡を取る必要があります。会社によっては、お香典や供花の準備、弔電の手配などを検討することもあるため、できるだけ早く電話で伝えましょう。
ご遺族の勤め先
ご遺族である方が会社員の場合は、早めに勤務先へ電話で家族葬の連絡をしましょう。葬儀の準備などで仕事を休む必要があるため、忌引き休暇の取得や業務の引き継ぎについて、上司や担当者に速やかに相談することが大切です。電話であれば、スムーズに調整が進むことが期待できます。
故人様と親しい友人・知人
故人様と深い親交があった方々には、葬儀前に伝えるのが理想です。ただし、家族葬の場合は参列者を限定するため、参列いただかない方には葬儀後に伝えることもあります。
参列いただく方には、葬儀の日程が決まり次第、電話で直接伝え、詳細はメールやはがきで補足するとよいでしょう。
町内会・自治会への連絡
ご近所の方々へ家族葬を周知する方法としては、まず町内会長や自治会長に電話で連絡します。家族葬であることを伝え、参列やお香典を辞退したい旨を丁寧に説明します。その後、回覧板などを活用し、近隣住民の方々へ情報が共有されるよう協力をお願いしましょう。
そのほかの家族葬に参列いただかない方
家族葬に参列いただかない方にも、故人様の訃報・葬儀に関しては伝える必要があります。
葬儀前は、電話での連絡が相手の理解を得やすいでしょう。一方、葬儀後の場合は、手紙やはがきなど丁寧な方法であれば、必要な情報やご遺族の心情を伝えられます。
葬儀後に連絡する場合も、お知らせが遅くなりすぎないよう、葬儀後のスケジュールも踏まえて連絡するようにしましょう。
5.家族葬の連絡をする際に伝える主な項目

家族葬の連絡をする際に、伝えるべき主な項目を解説します。相手とタイミングなどによって、どの項目を伝えるか整理してから連絡するとよいでしょう。
故人様に関わる情報
家族葬の連絡をする際に、故人様に関わる以下のことをしっかりと伝えます。
・故人の氏名
・亡くなった日時
・連絡者と故人の関係
・死因(必要に応じて)
なお、死因については、必ずしも伝える必要はありません。「かねてより療養中でしたが、安らかに永眠いたしました」など、必要な範囲で、簡潔に伝えます。
家族葬や弔問・弔意の品に関すること
家族葬を行う際、弔問やお香典、供花、お供え物を辞退する場合は、その旨を事前に伝えることが重要です。近親者のみで行う家族葬であり、ご遺族の意向や故人様の希望である点などを説明すると、相手の気持ちに配慮しつつ理解を得やすくなります。
葬儀の詳細(葬儀に参列いただく場合)
家族葬に参列いただく場合には、葬儀に関して以下の点を伝えます。
お通夜・告別式の日時
お通夜と告別式の日時を事前に知らせることで、参列者は予定を調整しやすくなります。ご遺族と参列者との間での時間的な誤解も避けられるでしょう。
会場の場所と連絡先
会場の場所を正確に案内し、アクセス方法や駐車場の有無、最寄り駅なども伝えると親切です。会場の連絡先も知らせておくと、参列者が当日、迷ったり、困ったりした際、迅速に対応できます。
喪主の名前と故人との関係
喪主様の名前と故人様との関係を伝えておけば、参列者は喪主様に対して適切な敬意を示すことができます。
葬儀の情報が広がらないためのお願い
参列者には、家族葬で参列者を制限しているため、葬儀に関する情報が広がらないようにお願いをします。
6.家族葬の連絡をするときの文例
喪主様がどのような立場であるかに応じても挨拶の内容は変わってきます。ここでは、喪主様の立場別での文例をご紹介します。
家族葬の連絡の内容は、葬儀前と葬儀後で異なります。それぞれの場合の文例をご紹介しますので参考にしてください。
葬儀前に連絡するときの文例
葬儀前に連絡する場合の文例をケースごとに分けて、注意点とともにご紹介します。
参列いただくご親戚への連絡
まずは電話で一報を入れ、その後メールなどで葬儀の詳細を伝えると、情報の伝え漏れや誤りを防げ、相手も後から確認できます。
◆第一報の電話の場合
緊急の連絡先を伝えると相手も安心します。時間帯に配慮し、ご親戚であっても必要があれば「朝早くにすみません」「夜分に失礼します」といった一言を添えるのが礼儀です。
【文例】
○○(自分の名前)です。突然のご連絡となりますが、
父○○(故人の名前)が、○月○日に永眠いたしました。
家族で話し合いまして、家族葬にする予定でおります。
葬儀の日程などが決まりましたら
メールかはがきで詳細をお知らせいたします。
何かございましたら、090-△△△△-△△△△まで、ご連絡ください。
どうぞよろしくお願いいたします。
◆電話をした後にメールをする場合
弔事での正式な文書では、句読点を使わないのがマナーですが、メールでは可読性を重視するため、句読点を用いても差し支えないとされています。
【文例】
〇〇様
先日、お電話にてご連絡いたしましたが、父・〇〇の葬儀につきまして
下記のとおりご案内申し上げます。
通夜:〇月〇日(〇曜日)午後〇時より
葬儀・告別式:〇月〇日(〇曜日)午前〇時より
場所:〇〇会館
住所:〇〇市〇〇町〇丁目〇番地
電話番号:〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇
喪主:〇〇(妻)
ご多用のところ恐縮ではございますが、
ご都合がよろしければご参列いただければ幸いです。
ご不明な点やご質問がございましたら、下記までご連絡ください。
何卒よろしくお願い申し上げます。
〇〇〇〇(差出人名)
住所:〇〇市〇〇町〇丁目〇番地
電話番号:〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇
メールアドレス:example@example.com
参列いただかないご親戚への連絡
参列いただかないご親戚への電話連絡では、家族葬であるため参列をご遠慮いただきたい旨を明確に伝えるとともに、「故人の遺志により」「会場の都合のため」などの理由を丁寧に説明します。日ごろ交流のないご親戚には、葬儀後に連絡する場合もあります。
【文例】
私、〇〇(故人名)の長男の〇〇でございます。
〇月〇日に母の〇〇が永眠いたしました。
葬儀に関しましては、故人の遺志により、
小さい式場で家族葬を執り行うこととなりました。
そのため、参列はご遠慮いただきますようお願い申し上げます。
詳細につきましては、後日改めてご連絡いたしますが、
何卒ご理解いただけますようお願いいたします。
自治体・町内会への連絡(電話)
自治体や町内会への電話は、日中の時間帯にかけ、簡潔に礼儀正しく、葬儀の日時、場所、家族葬であること、参列などを控えていただきたい旨を伝えます。「突然のお知らせで失礼します」など、相手への配慮の言葉も忘れないようにしましょう。
【文例】
突然のお電話、失礼いたします。
◯◯の息子の△△でございます。
父の◯◯が逝去いたしましたことをご報告させていただきたく
お電話を差し上げました。
葬儀については、故人の遺志に従い、家族葬を予定しております。
つきましては、たいへん恐縮ではございますが、
お香典・弔電・供花・供物などはご遠慮賜りますようお願い申し上げます。
近隣の方々にも、その旨お伝えいただければ幸いです。
何かご不明点等がございましたら、私のほうへご連絡ください。
念のため、私の電話番号をお伝えさせていただきます。
電話番号は090-0000-0000です。
どうぞよろしくお願いいたします。
後日に連絡するときのはがきの文例
葬儀の後日に連絡するはがきや手紙などの書き方は、下記の点に注意が必要です。
・時候の挨拶や「拝啓」「敬具」などの頭語・結語は使用しない
・死や不吉を連想させる忌み言葉、不幸が繰り返すことを連想させる重ね言葉は避ける
・句読点は使わず、文章を区切る際にはスペースを空ける
【文例】
〇〇年〇月〇日 〇〇歳にて永眠いたしましたことをご報告いたします
葬儀に関しましては 故人の意向により近親者のみで執り行いました
本来であれば 早急にお知らせすべきところ
ご連絡が遅れましたこと 心よりお詫び申し上げます
生前中に賜りました温かいご厚情に 深く感謝いたします
つきましては 誠に恐縮ではございますが
弔問 香典 供物などのご厚意はご遠慮させていただきたく
何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます
〇〇年〇月
〇〇県〇〇市〇〇町〇〇-〇
喪主 〇〇〇〇
7.家族葬は会社にはどう連絡する?
故人様が勤務されていた会社や、ご遺族ご自身の勤務先への連絡は、訃報の第一報としてできるだけ早く行うのが基本です。連絡は電話で、迅速かつ簡潔に伝え、詳細は後日改めてお知らせする形が望ましいでしょう。
ご遺族や故人様の会社に家族葬の連絡を電話でする際は、必要に応じて次の内容を含めることが重要です。
・葬儀は家族葬であること
・葬儀日・会場など、情報公開の範囲に関する希望
・弔問やお香典、供物などを辞退する旨
次項から、それぞれのケースにおける具体的な文例をご紹介します。
故人様の勤務先への連絡文例
故人様が勤めていた会社へは、まず迅速に訃報をお伝えし、その後に葬儀の詳細を連絡します。
1.訃報の連絡
【文例】
突然のご連絡で誠に恐縮ですが、先日、〇〇が永眠いたしました。
生前は大変お世話になり、心より感謝しております。
葬儀の詳細につきましては、改めてご連絡いたしますので、
まずは訃報をご報告申し上げます。
ご不明な点がございましたら、私までご連絡ください。
電話番号は090-0000-0000です。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
2.家族葬である旨の連絡
【文例】
〇〇(故人の氏名)の娘の△△と申します。
生前は父がたいへんお世話になり、誠にありがとうございました。
葬儀につきまして詳細が決まりましたのでお知らせいたします。
葬儀は、故人の遺志により、家族葬にて執り行うこととなりました。
そのため、誠に恐縮ではございますが、
弔問・お香典・供物などのご厚意は辞退させて
いただきますことをご理解いただけますと幸いです。
また、勤務先の皆様には、葬儀の日程や会場につきましては
内密にしていただけますようお願い申し上げます。
お手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
ご遺族が自分の勤務先に連絡する際の文例(忌引の連絡)
ご遺族がご自身の勤務先へ連絡する場合は、まずは突然の連絡となったことへの丁重な謝罪を述べましょう。その上で、忌引きを取得したい旨と、家族葬を執り行う予定であることを、簡潔に伝えます。
1.訃報の連絡
【文例】
突然のご連絡となり申し訳ございませんが、私の兄が先日急逝いたしました。
つきましては、葬儀等のため、
○月○日から○月○日まで忌引きをいただきたく、
ご相談のためご連絡いたしました。
詳細につきましては後日改めてご連絡いたしますので、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
2.家族葬である旨の連絡
【文例】
このたびは、急なことで皆様にはご迷惑をおかけしております。
今回の葬儀は、故人の遺志に基づき近親者のみで執り行う家族葬といたします。
そのため、香典・供花・弔電などご弔意につきましては、
誠に勝手ながら辞退させていただきたく存じます。
家族葬について会社に連絡する方法について詳しくは「家族葬は会社・職場にどう連絡すればいい?」の記事で解説しております。ぜひ、そちらもご覧ください。
8.家族葬の連絡をするときの注意点
家族葬の連絡をする際には、いくつか注意すべき点があります。こちらでは、主なポイントを解説します。
連絡するタイミングに配慮する
参列をお願いしたい方には、できるだけ早く伝えることが大切です。ただし、特に電話の場合は、深夜や早朝は相手の負担となることがあるため、日中の常識的な時間帯に連絡するようにします。
必要な情報を整理して簡潔に伝える
「家族葬の連絡をする際に伝える主な項目」でご紹介した、故人様に関わる情報、家族葬や弔問・弔意の品に関すこと、葬儀の詳細などを整理して簡潔に伝えます。必要な情報を事前にまとめておけば、連絡時に漏れや混乱を防げます。
相手の心情にも配慮する
家族葬に参列いただかない方へは、特に相手への心情に配慮が必要です。参列を遠慮していただく理由を丁寧に説明し、相手の気持ちに寄り添った言葉遣いをすることで、誤解を避け、円滑なコミュニケーションが図れます。
家族葬の連絡に関するQ&A
A.故人様が現役社員であった場合、勤務先への家族葬の連絡は早急に行うべきです。喪主様が会社員である場合は、まず直属の上司に伝え、その後、必要に応じて担当部署に連絡します。
故人様・喪主様の同僚や取引先への連絡については、状況を考慮しつつ連絡するかどうかの判断をしましょう。
A.故人様の近しい友人には、直接、電話をかけるか、メールで家族葬を行うことを伝えます。
その他の知人には、葬儀後に訃報とともに家族葬についても報告するケースが多いようです。参列を辞退していただきたい場合は、その旨を明確に、かつ「故人の遺志」「家族の希望」「会場の都合」などの理由を丁寧に伝える配慮が大切です。
A.訃報とともに、「家族のみで家族葬を執り行うため、親戚を呼ばない」旨を事前に電話で伝えるのが望ましいです。
ただし、普段から連絡を取っていない親戚には、葬儀後に家族葬を行ったことを正式な書面で報告しても問題ないでしょう。
10.家族葬の連絡は相手への配慮を忘れず慎重に行いましょう
家族葬の連絡は、相手への配慮を忘れず、誤解を招かないよう慎重に行うことが大切です。知らせる範囲や伝え方を誤ると、相手に不信感や戸惑いを与えてしまう場合もあります。適切なタイミングで、わかりやすく心を込めて伝えましょう。
家族葬の連絡の仕方に悩んだときは、一人で抱え込まず、花葬儀の事前相談をご利用ください。花葬儀では、経験豊富なスタッフが、家族葬の適切な連絡の方法やマナーについてもしっかりサポートいたします。大切な方を安心してお見送りできるよう、お手伝いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。




























