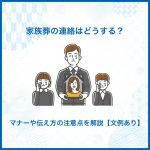火葬式(直葬)とはどのような葬儀?費用相場・内訳から流れ・注意点まで解説
- 作成日:
- 【 葬儀・葬式の基礎知識 】
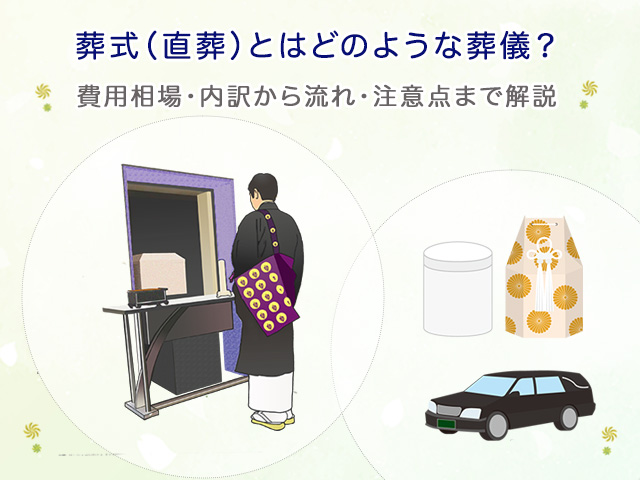
火葬式は、2000年台に広く認知されるようになった葬儀形式です。費用が抑えられる印象から、ご家族がいないおひとりさまや、ご家族に負担をかけたくない方が選ぶことが多いようです。しかし、「一般の葬儀とどう違うのか」「実際の費用はどのくらいなのか」といった疑問を持つ方も少なくないのではないでしょうか。
そこで今回は、火葬式の費用の相場から内訳、選ぶ際の注意まで詳しく解説いたします。火葬式を検討している方や興味を持っている方は、ぜひ参考になさってください。
1.火葬式とは

火葬式とは、通夜、葬儀・告別式などの葬儀儀式を一切行わず、火葬だけを行う葬儀形式です。故人様を安置した場所から直接火葬場に運び、火葬と収骨を行うことから、「直葬」とも呼ばれます。
火葬式ではお別れの時間が非常に短く、火葬炉の前で5分から10分程度の読経やお別れを行った後、すぐに火葬に移ることが一般的です。亡くなってから7日目に行う初七日法要も、火葬式と同時に行うことが多くなっています。
ごく少数で故人様とのお別れをしたい、あるいは、葬儀を安くすませたいなどと望まれるご遺族が、火葬式を選ぶ傾向にあるようです。気になる火葬式の費用の相場や内訳については、次項より詳しく解説します。
2.火葬式にかかる費用の相場
火葬式には、火葬場利用料や棺、搬送費などの固定費と飲食費、返礼品費といった変動費がかかります。
株式会社鎌倉新書が2024年に行った「第6回お葬式に関する全国調査」では、火葬式の費用総額は、平均42.8万円との結果でした。なお同調査によると、一般葬や家族葬などを含めた葬儀費用の総額の平均は約118.5万円でした。こちらと比較しても、火葬式の費用は安価であるといえます。
出典:第6回お葬式に関する全国調査(2024年)
調査主体:株式会社鎌倉新書
調査対象:2022年3月~2024年3月に喪主(または喪主に準ずる立場)を経験したことのある、日本全国の40歳以上の男女
URL:https://www.e-sogi.com/guide/55135/
3.火葬式の費用内訳|基本的に費用がかかるもの
火葬式で、基本的に費用が発生するものについて、それぞれの費用相場とともに解説します。
棺・骨壺などの葬祭品
棺や骨壺などの葬祭品は、火葬式を行う際に必要な固定費でもあります。いずれもさまざまな素材やデザインがあり、どれを選ぶかによって価格が異なります。
| アイテム | 説明 | 相場 |
|---|---|---|
| 棺 | 故人様を安置し、火葬場まで運ぶために使用 | 3万円~30万円 |
| 布団 | 故人様を棺に納める際に使用 | 1万円~3万円 |
| 死装束 | 故人様が着用する服 | 数千円~10万円 |
| 骨壺 | 火葬後の遺骨を納める | 1万円~10万円 |
ドライアイス
安置期間中、故人様のお体の腐敗を防ぐために、ドライアイスが必要です。通常、葬儀社が用意しますが、使用量や期間に応じて費用が計算されます。価格は地域や季節によって変動しますが、おおよそ1日当たり約5,000円~1万円となっています。
故人様の搬送
故人様のお体の搬送には、寝台車や霊きゅう車が使用されます。
・寝台車:亡くなった場所から自宅や葬儀社の霊安室などに運ぶ
・霊きゅう車:故人様を納めた棺を安置している場所から火葬場へ運ぶ
距離や時間帯によって搬送費用は変わってきます。10km未満の走行距離であれば、それぞれ約1万円~2万円、それ以上の場合は10kmごとに2,000円~5,000円が加算されます。深夜の搬送や待機の必要があれば、追加料金が発生することもありますので、留意しておきましょう。
安置所の利用
安置場所としては、ご自宅と、それ以外の専門の施設があります。病院で亡くなった場合であっても、病院内で故人様を長時間預かることは難しいことが多く、すぐに安置場所を確保しなければなりません。
故人様を安置する施設の使用料は、安置期間や施設の設備によって異なりますが、一般的には、1日当たり5,000円~2万円程度が相場とされています。なお、ご自宅に故人様を安置する場合は、搬送費やドライアイスなどの費用はかかりますが、安置所を利用する費用を抑えることができます。
火葬のための費用
火葬のための費用は、公営と民営の斎場(火葬場)で異なります。それぞれの特徴と費用相場をご紹介します。
公営斎場の場合
公営斎場は、市町村などの自治体が運営しており、斎場を運営する自治体に住民票がある居住者の使用については、一般的に低額な料金設定がなされている場合が多く、費用は無料~数万円程度です。
公営斎場は民間斎場に比べて費用を抑えることができるため、利用希望者が多く、希望する日時に利用できないことがあります。なお、公営斎場は基本的には住民登録をしている方のための施設であるため、他の地域の方は利用できなかったり、地域住民よりも割高になったりすることが多くあります。
民営斎場の場合
民営斎場は、民間企業が運営し、休憩室や控室、火葬炉などの設備やサービスの質にこだわっているため、費用が高くなる傾向にあります。費用は20万円~30万円程度とされていますが、地域や施設によって幅があるのが実情です。
多くの火葬場では大人、子どもなどで費用が異なり、子どもや胎児の火葬費は大人にくらべて低額に設定されています。
4.火葬式の費用内訳|場合により費用が発生するもの

ここまで、火葬式を行った場合にかかる基本的な費用について解説しました。ここからは、場合によって費用が発生するものについて、相場も含めて解説します。
宗教者へのお支払い
火葬式でも、僧侶を招いて読経をお願いすることがあります。その際は、僧侶に渡すお布施を用意しましょう。
火葬式におけるお布施の相場は3万円~10万円程度とされています。例えば、火葬場でのみ数分間の読経を依頼する場合は3万円、火葬場と安置所の両方で読経を行う場合は10万円といったように、依頼する内容により金額が変動します。お布施は僧侶への感謝の気持ちを表すものなので、失礼のないよう適切な金額を用意しましょう。
祭壇
火葬式では通夜や葬儀・告別式を省略するため、必ずしも祭壇は必要ではありません。祭壇を省略することで費用を抑えることも可能ですが、故人様への最後の敬意として、祭壇を設けるご家族も多くいらっしゃいます。
一般的な白木祭壇の費用は10万円~100万円以上、花祭壇は20万円~100万円以上と、グレードによってかなりの幅があります。
参列者へのおもてなし
お香典をいただいた方には、忌明け後に香典返しを送るのが通常です。香典返しでは、いただいたお香典の額の3分の1から約半分の品物を送ります。なお最近では、一律の金額のものを葬儀の当日にお渡しする当日返しが主流になりつつあります。
また火葬後に、精進落としと呼ばれる食事の席を用意する場合もあります。精進落としの費用は、地域や宗派によって異なりますが、1人当たり4,000円~5,000円程度が相場です。
その他、遠方から来ていただいた参列者にはお車代をお渡しすることもあります。
火葬場の控室
火葬場の控室は、ご遺族が火葬の準備が整うまでの間、または、火葬後の骨上げの儀式までの時間を過ごすために使用します。控室の利用には、火葬費とは別途、費用が発生します。使用料の相場は、公営斎場では無料~数千円程度、民営の火葬場では数万円程度です。
5.火葬式の基本的な流れ
火葬式の基本的な流れは、下記のとおりです。
1. 葬儀社と火葬式の日取りを決定
火葬式を行うことが決まったら、葬儀社と連絡を取り、火葬式の日程を決める。
2.納棺の儀
故人様を棺に納める儀式。これが故人様との最後のお別れの時間になる。
3.火葬式
納棺の儀の後、故人様を火葬場に搬送。火葬前に読経を行うこともある。
火葬後に精進落としを行うケースも。
4.収骨
火葬が終わった後、遺骨を骨壺に納める儀式を行う。
詳細については「火葬式の流れ」にて解説しておりますので、こちらもあわせてご覧ください。
6.火葬式のメリット・デメリット

火葬式にかかる費用や、火葬式の流れについて理解したところで、ここからはあらためて、火葬式を行うことのメリットとデメリットを解説します。火葬式を検討する際に、ぜひお役立てください。
火葬式を行うメリット
火葬式を行うメリットには、大きく次の2点が挙げられます。
短時間・低予算で行える
火葬式は、一般的な葬儀にくらべて、時間や費用を抑えることができます。通常の葬儀では、通夜や葬儀・告別式など複数の儀式を経てから火葬にいたりますが、火葬式ではこれらを省略し、直接火葬に進みます。通常2日間に渡って行う儀式の時間を数時間に短縮でき、葬儀の準備や弔問対応などにかかる時間的負担も軽減されます。
精神的な負担・労力を削減できる
火葬式は通夜や葬儀・告別式を行わないため、葬儀の儀式に関する打ち合わせが少なくなり、ご家族の精神的な負担も軽減されます。また、少人数で行うことが多いため、参列者への対応が少なくなることも、疲労を感じやすいご家族にとっては助けとなるでしょう。
火葬式を行うデメリット
火葬式には上に挙げたようなメリットがある一方で、以下のようなデメリットもあります。
十分なお別れの時間が取れない
火葬式の最大のデメリットのひとつは、故人様とのお別れの時間が限られてしまうことです。
通常の葬儀では、通夜や葬儀・告別式を通じて故人様との思い出を参列者の方々と共有するなどし、故人様とゆっくりと別れをする時間が確保されます。しかし、火葬式ではこれらの儀式が省略されるため、必然的に、ご遺族が故人様との最後に過ごす時間が少なくなってしまいます。
ご親族・寺院に抵抗感があることがある
もうひとつのデメリットは、一部のご親族や寺院から抵抗感を示される場合があることです。
火葬式は、比較的新しい葬儀の形式であり、宗教的な価値観を大切にするご親族や、菩提(ぼだい)寺からは、理解を得るのが難しい場合があります。無理に火葬式を選ぶと、関係悪化を引き起こすことにもなりかねません。
7.火葬式を行うときに注意したいこと

火葬式を行う際には、メリット・デメリットに加えて、以下の点にも十分注意を払っておきましょう。
安置日数に応じた費用が他の葬儀形式と同様に必要
火葬式を行うまでの間は、故人様を安置する費用がかかります。これは火葬式に限らず、他の葬儀形式でも同様です。
なお日本では、法律により故人様が亡くなってから最低24時間は火葬を行ってはならないと定められています。そのため、安置期間は通常、どのような葬儀形式であっても、ご逝去から数日程度はかかります。
関東地域では特に、高齢化による死亡者数の増加から火葬場の予約が取りづらくなっていることから、「亡くなってから約1週間」が葬儀の目安となりつつあり、今後さらに期間が延びる可能性もあります。
葬儀プラン・見積もりは十分に比較検討
火葬式をする際には、複数の葬儀社の葬儀プランや、見積もりについて、慎重に比較検討することが重要です。同じ火葬式といっても、葬儀社によって提供されるサービス内容や価格には大きな差があるため、複数の葬儀社から見積もりを取り、内容を比較することをおすすめします。
見積もり際には、総額としていくらの費用がかかるかを確認することが重要です。追加費用が発生する可能性のある項目も確認しておきましょう。「火葬式〇万円」といった料金を掲げているサイトなどもがありますが、条件によっては追加費用が発生する可能性があるため、明確な見積もりを提示してくれる葬儀社を選ぶことが大切です。
お付き合いのある寺院があれば事前に相談
特定の宗派に属している場合や、菩提(ぼだい)寺との関係がある場合には注意が必要です。お寺によっては、火葬式での納骨を快く思わないこともあります。トラブルを避けるためにも、事前にお寺に火葬式での納骨が可能かどうか相談しておきましょう。
8.【花葬儀】火葬式でもオーダーメイド花祭壇で悔いのないお別れができる
通常の葬儀に比べ時間が短い火葬式であっても、故人様をしのぶという葬儀の意義を大切にしながら執り行うことが大切です。弊社「花葬儀」では、死装束や後飾り祭壇のご相談を承り、僧侶による読経なども必要に応じて手配いたします。
また、大切な方への思いを形にされたい方のために、生花で作るオーダーメイドの花祭壇を組み込むことも可能です。花葬儀が提供している葬儀プランの中には、「花祭壇も組み込める火葬式プラン」もございます。火葬式と花と両方を希望される方は、ぜひ、ご相談ください。
9.火葬式はご親族や菩提寺と相談しながら決めましょう
火葬式は、一般的な葬儀と比較して安価で、時間・労力もかからないため注目されています。しかし、デメリットを十分に理解せず火葬式を選び、後悔するケースもあるため、安易に決定しないことをおすすめします。
火葬式を検討される際は、ご親族やお付き合いのある寺院とも十分に話し合うことが大切です。あわせて、火葬式のメリットだけでなく、デメリットについても丁寧に説明し、選択肢を示してくれる葬儀社を選ぶことが重要になります。
火葬式に関して疑問や不安をお持ちの方は、ぜひ花葬儀の事前相談をご利用ください。経験豊富なスタッフが、お客様の疑問に真摯(しんし)にお答えいたします。